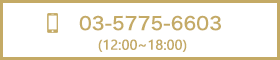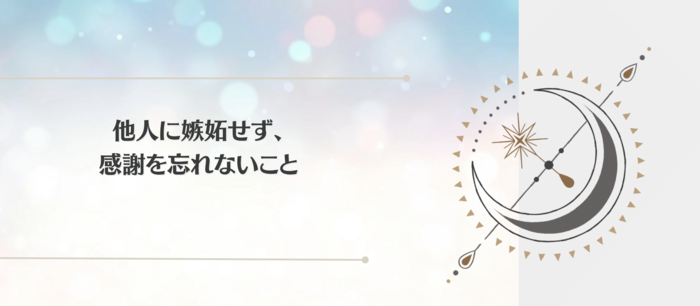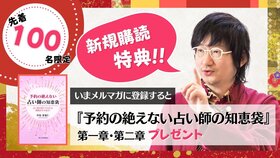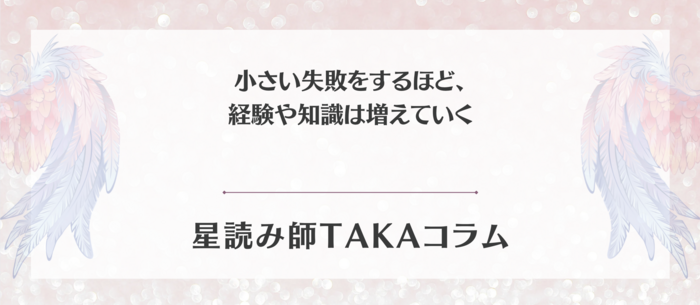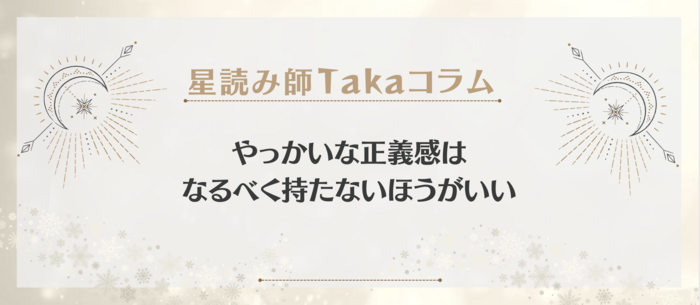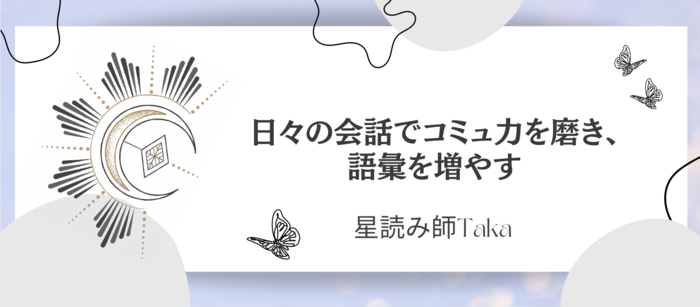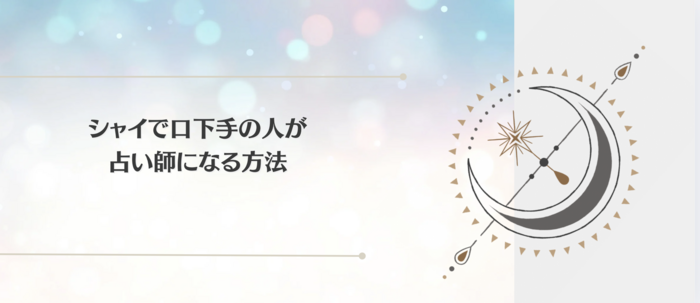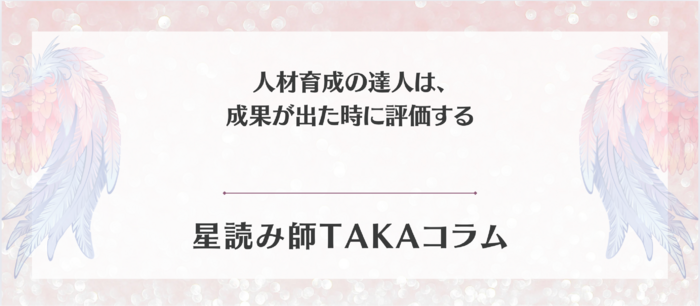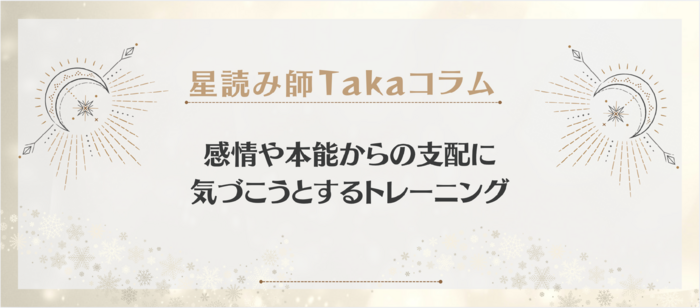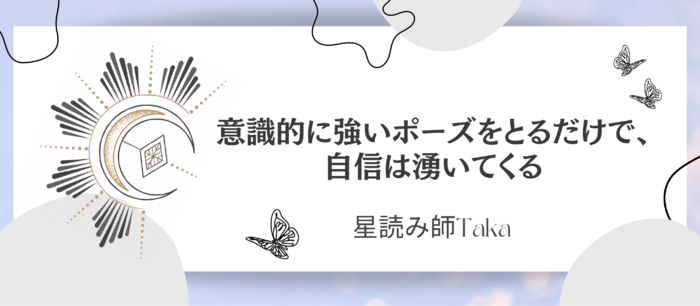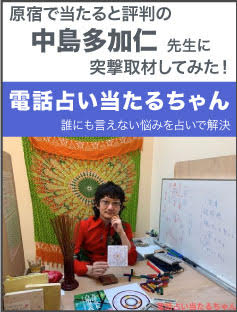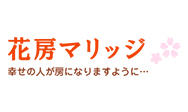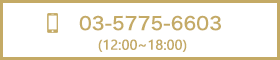他人に嫉妬せず、感謝を忘れないこと
今日は、幸せになる人と成功する人との共通点を探してみましょう。幸せになる人と成功する人、彼らは似ているのです。それは、ねたみ・そねみの感情が弱く、自分のやるべき使命を全うしている、という点です。幸せな人や成功する人は、第三者から嫉妬されます。でも、自分が誰かを嫉妬するなんてしません。
「ねたみ」とは、他人の幸運や長所をうらやんで、その邪魔をしたいという気持ち。
「そねみ」とは、他人の幸運や長所を見て、自分にそれがないと不満に思い、相手に悪いことが起きればいいのにと願う気持ち。「妬み」はやきもち。「嫉み」はヒステリー。両方合わせて「嫉妬」になります。
嫉妬が強いと、なかなか成功できないんです。なぜなら、嫉妬心から生まれた成功願望は、陰の気を発するからです。嫉妬する人は、無意識に「自分が成功すると嫉妬される」「幸せになると嫉妬される」と思っているのです。
頭でそう考えるのではなく、心のなかで思っている感情です。だから、「嫉妬されるくらいなら不幸でいい」という発想につながるので、成功しないんです。しかも、陰の気を発するので、えげつない人脈が集まってきます。周囲が、嫉妬しやすいタイプの人で構成されてしまいます。
富を得ることだけが、幸福ではありません。喜びを分かち合える仲間が、最高の財産なのです。嫉妬やひがみのないシンプルな関係です。
世間には、政治一家とか、事業一家という、家系がありますよね。そうした家系は、先祖代々お墓を大切にして、先祖供養をきちんとやっているから『徳分』や『福分』があるのです。生まれながらの『福分』は、四柱推命や紫微斗数という命理占で分かります。
『徳分』とは、目に見えない幸運の貯金です。芸能界だって、美貌と才能だけでは成功しません。前世の徳分が必要なのです。それが美人や天才に、生まれ変わる要素なのです。
人気のある女優やアーティストという人たちは、前世で僧侶やシスターで、神仏に仕えた人が多いのです。前世で神に仕えた人が、今世で成功しているわけです。
ぜひ次の世では、いまよりも美貌と才能に恵まれて生まれたいですよね。もちろんそれは可能です。今の世を、精いっぱい生き抜くことです。現実逃避をせず、課題から逃げないで、やるべきことをやるのです。他人に嫉妬しないで、自分の人生を楽しむのです。
それにはまず、感謝を忘れないこと。「感謝しろ」と言っているのではありません。感謝なんて、意識してするものではありません。ただ、感謝を忘れてはいけないんです。