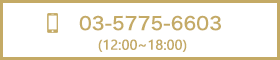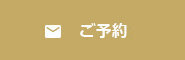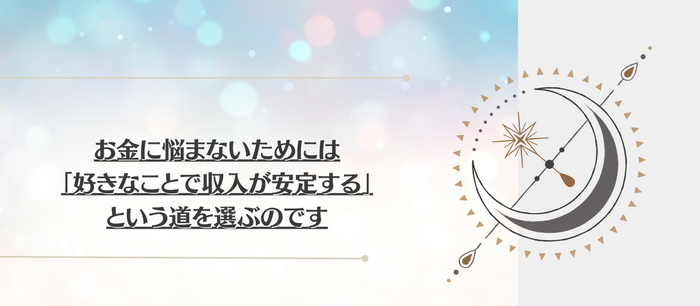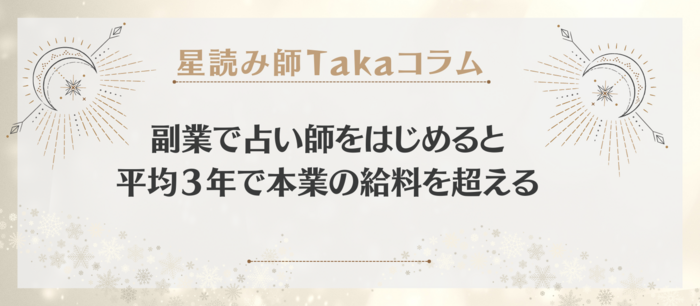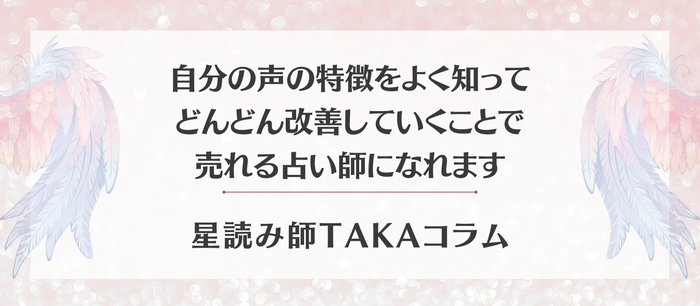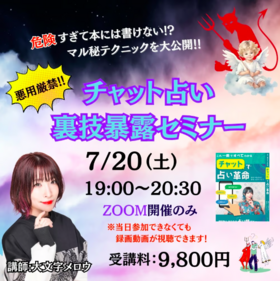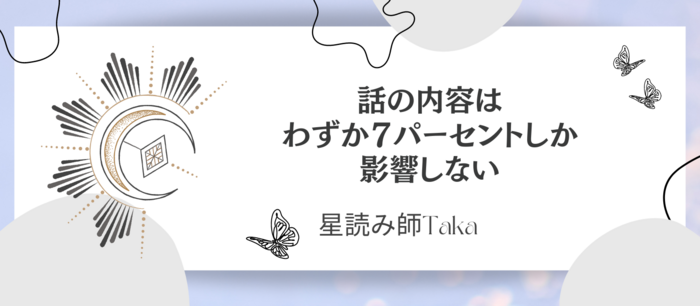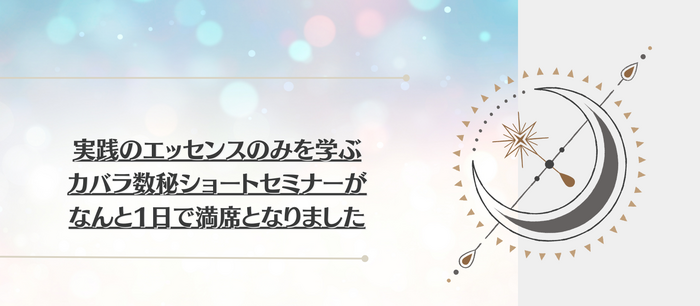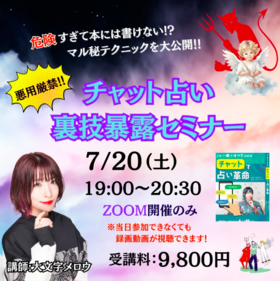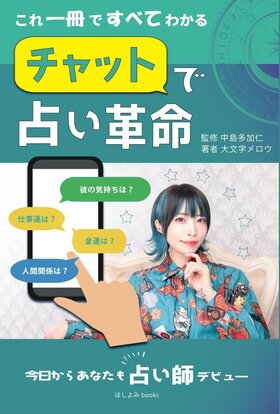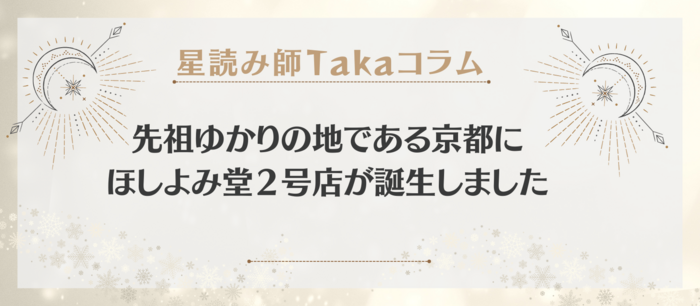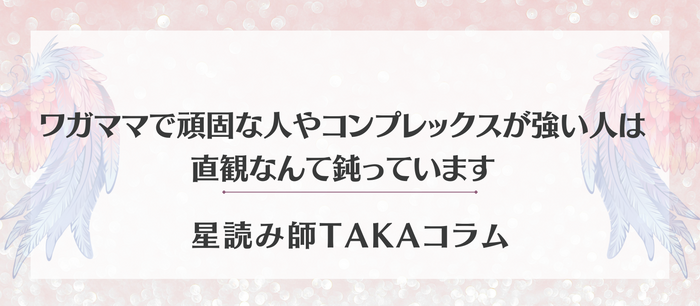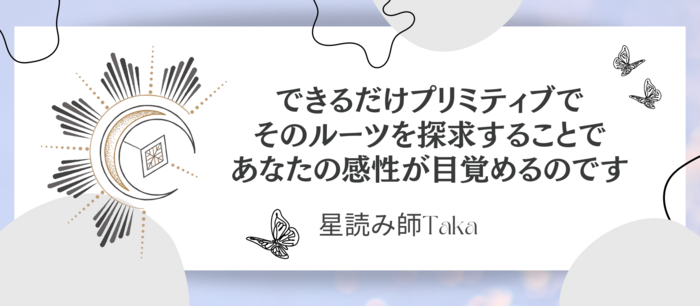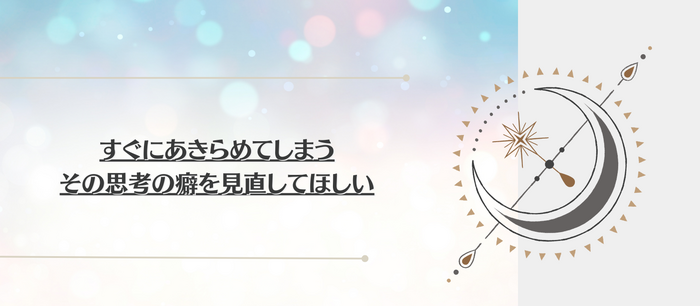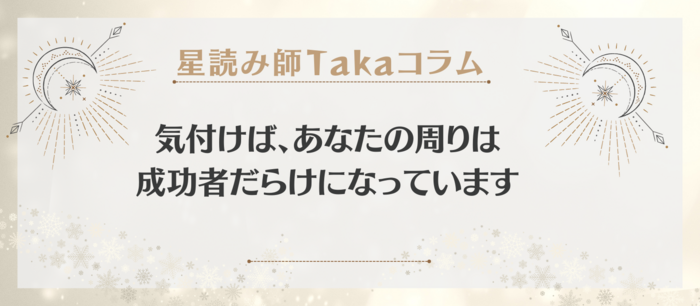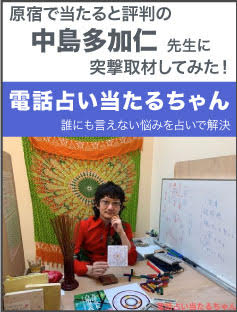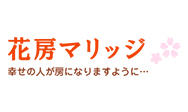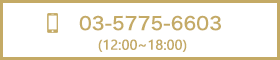お金に悩まないためには「好きなことで収入が安定する」道を選ぶのです
クラウド総合鑑定サービス『ほしよみシステム』は占い師必須アイテムです。生年月日を入力するだけで四柱推命・紫微斗数・九星気学という3つの占術に加えて、姓名判断と数秘術を一括表示できます。ありそうでなかった斬新な占いシステムです。
ぼくは朝起きると「さぁ今日も楽しい一日の始まりだ!」という気分になります。毎日そんな快適ですがすがしい朝を迎えています。自分の時間を、すべて、やりたいことに使います。これは、ぼくの理想そのもの。豊かさとは、『やりたいことを、やりたい時に、やれる能力』だと、考えています。
あなたは現在の月収に、不安を感じていませんか?専業主婦の方でしたら、もしご主人の仕事がなくなったらどんな気持ちになりますか?月々の固定の支払いをはじめ住宅ローンなど、子どもの学費に関して不安が生まれる可能性ありますか?
子どもが育つにつれて、どんどん膨らむ教育費。その教育費を使うことで、老後の蓄えは大丈夫ですか?将来の年金について、老後の生活には安心ですか?当たり前だけど、誰もが「幸せになりたい」「自由になりたい」と願っているはずです。しかし現実は不自由であり、出費に不安を持ち、人間関係にイライラする。
そのような悩みを抱える人に、ぼくは『自立すること』をお勧めします。自立っていうのは、お金が障害にならないんです。大切な人たちと過ごす時間がいっぱいとれるんです。
あなたが一番やりたいこと…
大切な時間を、思う存分それに使える。そんな状態を『自立』というのです。想像するだけでワクワクするはずです。子どもとの時間を大切にしながら、家事をおろそかにすることなく好きな仕事や趣味ができる。それが可能なのです。
好きなことをしないと、真の豊かさは手にできません。
人は自分の好きなことをして、ワクワクする感情を抱くことで、希望を持つことができ、裕福で幸せになることができます。好きなことをしていたら、夢中になるでしょう。だから、自分の本当の力が発揮できるのです。
いやいや仕事をしている人に、お金は巡ってきません。浅はかな人たちは、自分の大切な時間を売ることでお金を手にしています。好きじゃない仕事をすることで生活を安定させようとします。望むものが大きくなれば、必要なお金の額は大きくなります。すると、いやいや働く時間も増えてしまいます。収入が増えるほど、自由な時間が減っていく。お金が増えても、豊かさと離れていくのが現実のようです。
悲しいことに、お金というものは生きていくのに必要であり、ときに人を苦しめます。不安の材料にもなる…それが、お金です。そこで、ぼくはお金に悩まない生き方を提案しているのです。お金に悩まないためには、「好きなことで収入が安定する」という道を選ぶのです。
もちろんそんな夢のような話、すぐに実現できません。が、段階的に考えることで、経済的に自由な生き方が構築できるのです。いきなりではなく、少しずつ現状の生活を改善していくというやり方です。